ブロガーのなかじさんが自身のYouTubeチャンネル『ウェブ職TV』で紹介されていた中の1冊です。
なかじさんを知ったのは、元々はリベラルアーツ大学の両学長がご紹介されていた事がきっかけ。
私はリベシティの住民なのですが、その辺はまた別で語っていこうかと思います。
紹介されていた中で帯に挿絵が入っていて、これなら初心者でも読みやすいかもと思ったので、この「沈黙のWebライティング」を選びました。
いざ実物を見てみたら、え、、分厚。。。
うーん、これ、読めないかも、、と思ったのが第一印象でした。
気になって測ってみたら約3cm。
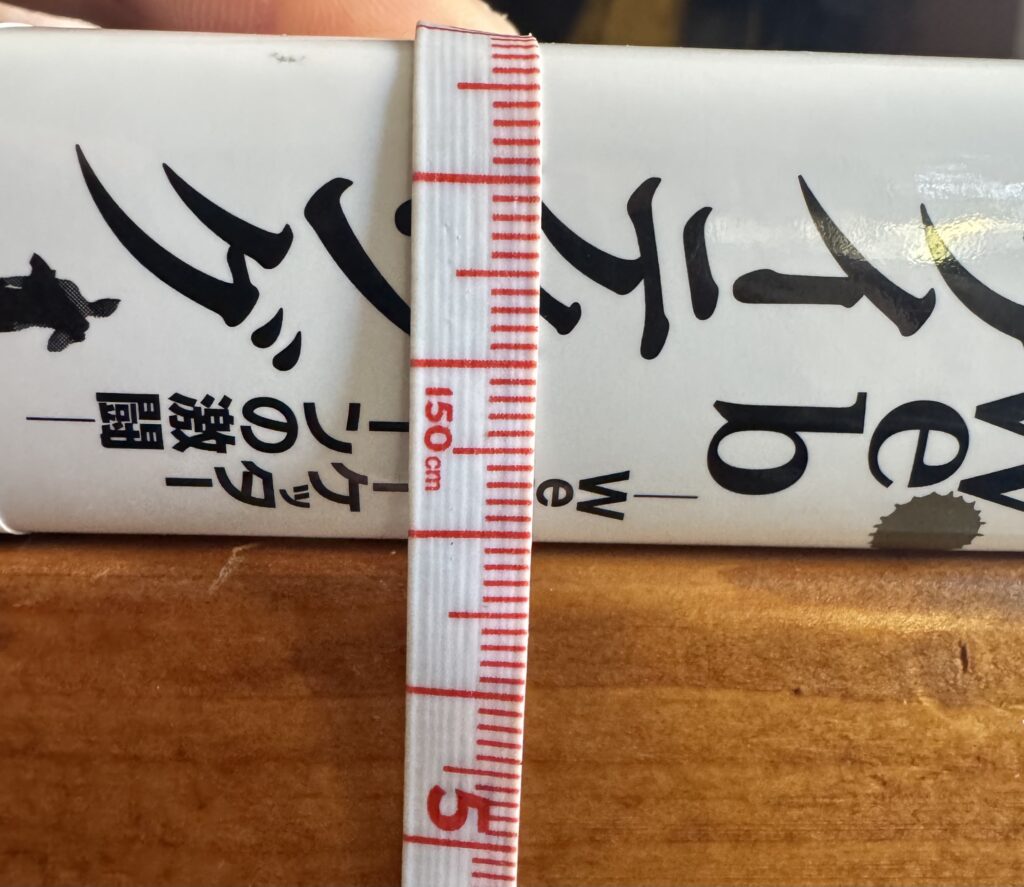
・
・
うん、いらんことした。
でもまあ、、せっかく買ったんだし、読まないことには始まらないなと。
ブロガーとして生活していきたいと決めていたので、意を決して読み始めました。
読み始めていくと、、あれ?、スルスル読める!(一気に本の1/6ページまで読んでしまいました)
まるでゲーム攻略本のようでNPCと会話しているような感覚。(子どもの頃ゲーマーだったので)
1ページの文字数も少なく、挿絵も入りチャット形式で物語が進んでいくので非常に読みやすい。
SEOだとかUSPだとか、意味はちゃんとわかっていない横文字に惑わされず、
ブログを書き始めて3ヶ月くらいの初心者〜中級者にこそ、意味を理解できるようになり、自分のブログがどこにつまづいてて、何が悪いのか、解決方法も載っていて読み進めて行くにつれて面白くなっていく本だと思います。
ストーリー形式で、理解できてなくてもついつい先を読んでしまいます。
そうする読んでいくのが億劫になりますので、お気をつけください。
自分が実践しているところまで読んで、実践して、の繰り返しで読んでいくのがおすすめです。
「沈黙のWebライティング」では栃木の温泉旅館「みやび屋」を舞台に、物語が進みます。
若女将のサツキと弟のムツミが、訳あって自社ホームページでの予約のみに頼っているため、予約数が取れず経営状態が日に日に悪くなっている状況
そこに現れたヴェロニカとWebマーケッターを名乗るボーン・片桐という謎のふたり
みやび屋に泊まる予約をしているこのふたりが、急にみやび屋のサイトは危ないと警告する
ムツミがSEOを意識し自社サイトの文章を書き換えたことにより、不自然な文章になっていることを指摘され、サイト改善のアドバイスをすることになった
エピソード①SEOライティングの鼓動
まずSEOとは•••
検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)のこと
Webサイトが検索結果でより多く露出(上位表示)するために行う一連の施策を指します。
わかりやすく言うと、
Googleなどの検索エンジンで何かのキーワードを検索したときに、そのキーワードで自分のサイトが上位表示されるように、サイト内の文章を書き換える作業のこと
検索意図と検索結果の関係について
今の検索エンジンは使う人たちがどういう意図をもって検索しているかという「検索意図」を推測して検索結果を返しています。
この根拠として、「Googleが掲げる10の事実」のページを確認してみてください。
Googleはユーザーにとって最も利便性の高い検索結果を返そうとしている、という事がわかります。

沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘— アップデート・エディション
エピソード②解き放たれたUSP
USPとは•••
他社にはない独自の強み(Unique Selling Proposition)のこと
自分が何かの商品を売りたい時、その商品のUSPを伝えることは他社商品との比較ポイントを伝えることになる
USPを決める際に重要な2つのポイント
・競合に真似されにくいこと
・競合と同じステージで戦わずに済むこと
たとえば、サツキたちは親孝行プランという独自のプランを打ち出し、みやび屋のUSPにしました。
これは両親を早くに亡くし、親孝行したくてもできなかったという思いがあるからこそ成立したUSPで、競合が真似したくてもできません。
このUSPを理解するのに成功事例として、「沈黙のWebライティング」では実際にあるサイトを例に説明してくれています。
エピソード③リライトと推敲の狭間に(読書中)
ボーン・片桐が
「人の心を動かすエモーショナルな文章を意識しろ」
「こんな文章では人の心を動かせん」
とUSPを元にコンテンツを作り直したムツミに対して厳しい言葉を投げかけた
そこでリライトするために重要なことを教えてもらうことになる
文章を読んでもらうために重要なことは
・感情表現を入れじぶんごと化によって共感を誘発することを意識させる
・思わず読み進めたくなるように、適度な興奮を感じさせる
・読み手の脳の負担を減らす
改行や行間が配慮されていない文章
休符のない文章、つまり行間のない文章は読む側を疲弊させてしまう
文章がかたまりになっていて読みづらい
改行や行間が配慮されている文章
句点(。)が出るたびに改行している文章は読みやすい
これはスマートフォンで文章を読むと違いがわかりやすい
漢字とひらがなの含有量を調整する
漢字だらけの文章は難しく感じられる一方で、ひらがなの多い文章は理解がかんたんすぎるのでちょうど良いバランスを意識する
「この」「その」「あの」などの指示代名詞を減らすと文章が読みやすい
読み手が文章の途中から読んでも、主語が何を指しているのかをわかりやすくするため

沈黙のWebライティング —Webマーケッター ボーンの激闘— アップデート・エディション
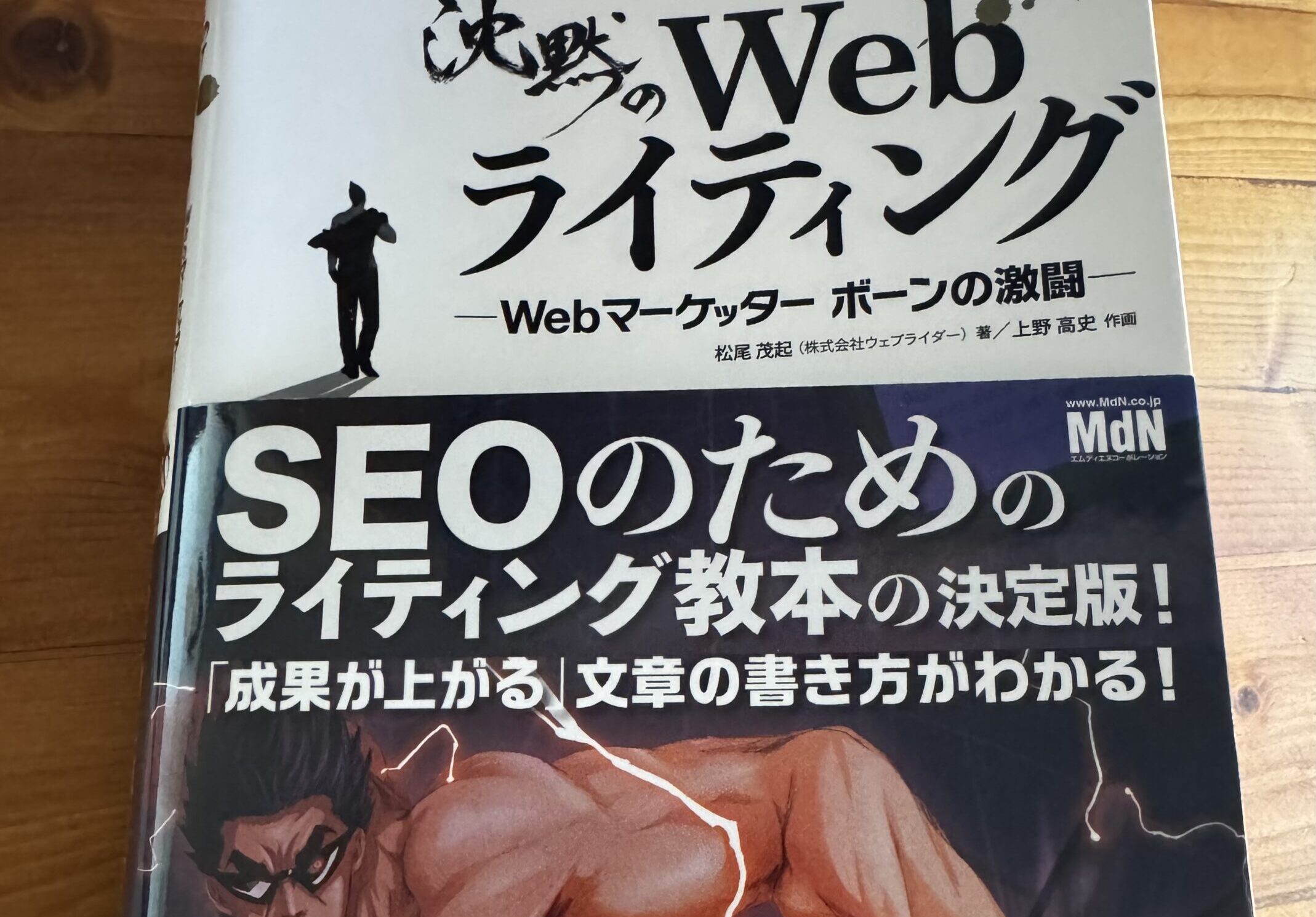


コメント